「どうしてあの人といると、自然とやる気が湧いてくるんだろう?」
あなたの周りにも、そんな“やる気にさせるのが上手い人”がいませんか?言葉や態度が不思議と前向きな気持ちを引き出してくれて、自分でも気づかない力を発揮できるような存在――。
この記事では、やる気にさせる人の特徴を心理学的な視点からわかりやすく解説しつつ、日常で使えるコミュニケーションのヒントも紹介します。
元全国大会経験の卓球選手として、僕自身がチームのモチベーションづくりで学んできたことも交えて、「どうすれば人はやる気になるのか?」を一緒に紐解いていきましょう。
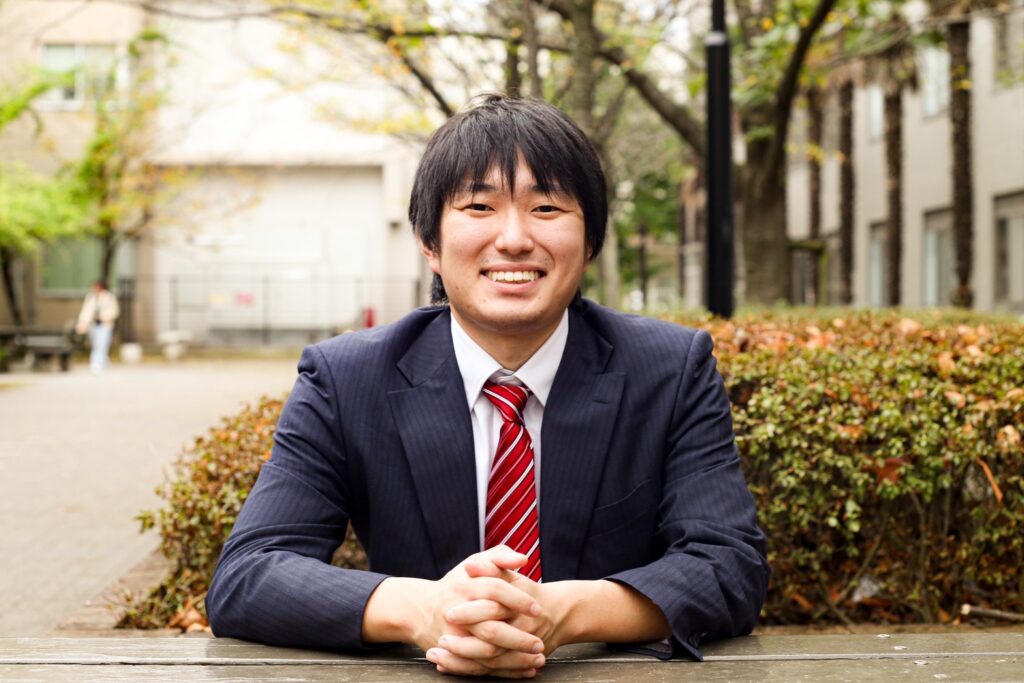
大戸 勇輝(おおと・ゆうき)/株式会社マイビジョン 採用コンサルタント
愛媛県在住、24歳。趣味は中学から続けている卓球🏓。
現在は、ベンチャー企業で6社の採用支援を担当しながら、ブログ運営やX発信を通して「習慣・継続・挑戦」のマインドを届けています。
もともとは“継続が苦手な人間”でしたが、そこから全国大会出場やブログ月28万PV、個人事業での月収5〜20万円達成など、小さな積み重ねで道を拓いてきました。
「後輩や家族に、ずっと頼られる人間になりたい」──そんな思いを胸に、日々コツコツと自分磨き中。
この記事では、そんな僕が実践してきた視点から、「物事を成功に導くマインドセット」についてお話しします。
【僕がXで「発信」をする理由】
— 大戸勇輝|元卓球全国出場のコーチング🏓 (@yuki0629_mv) June 25, 2025
大学3年の冬、コロナで部活が止まった。
大会も練習もなくなって、気づけば同級生は次々と引退。
それでも、僕は卓球を続けることを選んだ。
ただその時、正直すごく悩んだ。
「1人だけ残って浮かないかな」
「後輩たちに気を遣わせないかな」… pic.twitter.com/D6VEHeZSNb
やる気にさせるのが上手い人の特徴!
やる気にさせるのが上手い人は、いわば「無意識のうちにマネジメントができている人」とも言えます。部下や仲間のパフォーマンスを自然と引き出せる人たちには、いくつかの共通点があります。その中でも特に大切なキーワードが「心理的安全性」と「即時フィードバック」です。
心理的安全性がやる気を支える土台になる
心理的安全性とは、「この場では自分らしく発言しても大丈夫だ」と感じられる状態のこと。ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が提唱したこの概念は、Googleの生産性調査でも注目されました。
たとえば「こんなこと言ったら怒られるかも…」と感じる場では、人は萎縮して力を発揮しにくくなります。逆に「失敗しても受け入れてもらえる」と感じられる環境では、挑戦や発言が増え、結果的に自発性とやる気が育まれるのです。
即時フィードバックでモチベーションを維持する
やる気に火をつけるには、「タイミング」が非常に重要です。特に、良い行動に対するポジティブなフィードバックを即座に返すことが、やる気の維持につながります。
たとえば「今の声かけ、すごく助かったよ!」とその場で具体的に伝えるだけで、相手は「自分の行動が価値あるものだった」と実感できます。これは、心理学でいう「強化理論」にもつながり、行動の再現性を高める要素となります。
1-2. 「魔法の言葉」10選
やる気を引き出すコミュニケーションにおいて、言葉の選び方は非常に重要です。ちょっとしたひと言が、相手の気持ちを前向きにしたり、自信を与えたりする力を持っています。
ここでは、日常でもすぐ使える「魔法の言葉」を10個ご紹介します。どれもシンプルですが、心理学的にも効果が実証されている言葉ばかりです。
✅ 1.「ありがとう」
- 効果:自己効力感を高め、関係性への安心感を生む
- → 感謝は「自分は役に立てた」という実感を与え、行動の再現性を高めます。
✅ 2.「助かったよ」
- 効果:貢献感を高め、相手の承認欲求を満たす
- → 行動を評価するだけでなく、直接的に「あなたのおかげ」と伝える一言です。
✅ 3.「よく見てるね!」
- 効果:観察力や気づきを褒めることで、思考力を承認する
- → 結果だけでなく「過程」を評価する姿勢が、やる気を促進します。
✅ 4.「あなたならできると思った」
- 効果:期待と信頼を明確に伝える
- → ピグマリオン効果(期待が成績を左右する)を活かした言葉です。
✅ 5.「どう感じた?」
- 効果:内省を促し、自発的な動機づけを生む
- → 答えを与えるより、考える余白を与える方が動機は内側から育ちます。
✅ 6.「やってみてどうだった?」
- 効果:成功失敗に関わらず挑戦を認める
- → 結果だけでなく「経験」を承認する視点です。
✅ 7.「ここまで来たんだね」
- 効果:プロセス志向のマインドセットを育む
- → 成長の可視化は、継続のやる気につながります。
✅ 8.「それ、おもしろいね!」
- 効果:意見の価値を認め、発言の安心感を生む
- → 意見が受け入れられると、人は発信し続けようとします。
✅ 9.「安心していいよ」
- 効果:心理的安全性を直接的に伝える
- → 特に新しい挑戦や失敗を恐れる人に効果的です。
✅ 10.「信じてるよ」
- 効果:無条件の承認を示す言葉
- → 自分を信じきれないときこそ、他者からの信頼が力になります。
こうした言葉は、意識して使い慣れることで自然に出てくるようになります。僕自身もコーチングの現場で何度も「ありがとう」「助かったよ」を口にしてきましたが、それだけで相手の表情が変わる瞬間を何度も目にしてきました。
次章では、こうした言葉の土台にもなる「五感を活かしたモチベーションづくり」についてお話しします。
1-3. 一瞬でやる気 → 視覚・聴覚の活用
「なぜか急にやる気が出ない…」
そんな時、意志の力だけでモチベーションを引き出すのは簡単ではありません。むしろ、やる気が出ないのは“意志の問題ではなく、環境の設計”が原因かもしれません。
ここで活用できるのが、**視覚や聴覚といった「五感」**の刺激です。心理学的にも、人は五感を通じて感情や行動のトリガーが作られます。
🔊 音楽:感情を直接動かすスイッチ
脳科学の研究でも、音楽はドーパミン分泌を促すことが明らかになっています。たとえば、以下のような方法は多くの人に効果があります。
- プレイリストの活用:「集中用BGM」「やる気アップ音楽」などシーン別に分けておく
- 試合前のルーティン曲:僕自身、卓球の大会前には必ず聴く曲がありました。音が“スイッチ”になるのです。
🎥 動画・映像:モデリングの力を活用
心理学では「モデリング効果」と呼ばれ、他者の行動を見ることで自分もやる気になる現象があります。
- モチベーション動画:YouTubeなどで「夢を追う人」「努力の積み重ね」系の動画を見ると、自分の原点に立ち返れます。
- 目標に近い人のVlogや講演:リアルな努力のプロセスに共感することで、自分も一歩踏み出しやすくなります。
🏃♂️ 運動:身体が先、気持ちは後
やる気を出すには「まず動く」が最も効果的です。運動はセロトニンやエンドルフィンといった気分を安定させる神経伝達物質を分泌し、気持ちの切り替えに有効です。
- 散歩やストレッチ:2〜3分の軽い運動でもOK。机に座っているだけでは切り替わりにくいときほど効果的です。
- 「動きながら考える」習慣:僕も記事構成を考えるとき、あえて歩きながらメモをとることがあります。動くとアイデアも流れ出します。
1-4. 成功失敗の差を分ける叱り方・褒め方
やる気にさせるのが上手い人は、「伝え方」にも細やかな配慮があります。とくに“叱る”と“褒める”という両極のアプローチには、その人の人間観や信頼関係の深さが表れます。
上手に叱ったり褒めたりできる人は、相手の「自尊心」を守りながら、行動変容を引き出すことができるのです。
⚠️ 叱り方:人格ではなく“行動”にフォーカス
失敗したとき、やる気を削ぐ伝え方の典型が「なんでそんなこともできないんだ!」という人格否定です。これは自己肯定感を傷つけ、挑戦意欲を失わせてしまいます。
効果的な叱り方のポイントは次のとおりです。
- 事実に基づいて伝える:「今回のプレゼン、事前準備の時間が少なかったのが原因かもしれないね」
- 次の改善を提案する:「次は◯日前までに資料を整えておくと、もっと伝わると思うよ」
- 感情より意図を伝える:「驚いたけど、君ならもっとできるって思ってるからこそ伝えたんだ」
叱ることで信頼が深まるコミュニケーションは、「信じている」という前提があってこそ機能します。
🌱 褒め方:結果よりも「プロセス」と「姿勢」に注目
褒め言葉は、使い方を間違えると「その場しのぎ」になってしまいます。大切なのは、具体性と誠実さです。
効果的な褒め方のポイントは以下のとおりです。
- プロセスを具体的に褒める:「提出資料、構成がすごく整理されててわかりやすかったよ」
- 努力や工夫を拾う:「毎回、会議の前に下調べしてるよね。その姿勢がチームの支えになってる」
- タイミングを逃さない:評価の言葉は“行動直後”が最も効果的
心理学でも「即時強化」が重要だと言われています。良い行動はすぐに承認することで、次回以降のモチベーションが上がります。
僕自身も、学生時代の卓球チームで、何度も失敗を重ねた後に「次はどうすればいいと思う?」と問いかけてくれた監督の言葉が、今でも忘れられません。叱るでも褒めるでもなく、信頼と期待がセットになったコミュニケーションは、心の奥深くに届くものです。
次章では、そんな「やる気にさせる人」とそうでない人の違いを、僕自身の経験からご紹介していきます。
1-5. 実体験:上手い人・下手な人の違い
やる気にさせるのが上手い人とそうでない人――その違いは、僕自身のこれまでの経験の中でも、はっきりと感じる場面がいくつもありました。
僕は学生時代、卓球の全国大会に出場した経験があります。当時所属していた部活には、2人の指導者がいました。技術的な指導はどちらも一流。でも、僕たち選手のやる気や行動には、明確な差が出ていたのです。
🎯 上手い人:内発的なやる気を引き出す
Aコーチは、技術よりもまず「選手の話をよく聴く」人でした。うまくいったときは「どこが良かったと思う?」と問いかけ、失敗したときも「何にチャレンジしたの?」と行動の意図に耳を傾けてくれました。
その姿勢が「自分で考えて動く」土壌を育て、チームの雰囲気も前向きでした。僕自身も、試合でミスをしても「チャレンジできた」と感じられ、次に向かう気持ちを保てたのを覚えています。
❌ 下手な人:行動より“結果”だけを評価する
一方でBコーチは、結果が出たかどうかで態度が一変するタイプでした。勝てば賞賛、負ければ叱責。何より辛かったのは、「言われた通りやったのに怒られる」という感覚です。
やがて選手たちは、「ミスしないこと」「叱られないこと」が最優先になり、挑戦や自主性が失われていきました。中には、心が折れて競技を離れた仲間もいます。
💡 気づいたこと:大切なのは“どんな視点で関わるか”
卓球の現場だけでなく、社会人になってからの対人コーチングでも、この違いはよく感じます。人をやる気にさせる人は、「コントロールする」のではなく、「その人が本来持つ力を引き出す」ことに意識を向けているのです。
上司・コーチ・親――立場を問わず、関わり方ひとつで相手の行動も感情も大きく変わります。
やる気を引き出す関わり方は、特別な才能ではなく、ちょっとした意識と習慣の積み重ねで誰にでも身につけられるスキルです。
次章からは、「人をやる気にさせる心理学」の具体的な理論とテクニックを紹介していきます。
2-1. アドラー心理学「勇気づけ」の視点
やる気を引き出す上で欠かせない視点のひとつが、アドラー心理学における「勇気づけ(Encouragement)」です。アドラーは、「人が行動するには“勇気”が必要であり、他者の関わりでその勇気は育まれる」と説きました。
ここでいう勇気とは、「困難を乗り越える力」「自分にはできるという信念」のこと。つまり、やる気の根底には「自信」と「目的意識」があり、それを育てる関わりが“勇気づけ”なのです。
🎯 目標の「見える化」でやる気が生まれる
人はゴールが曖昧なままでは、力を発揮しづらいものです。逆に「目指す地点」と「そこまでの道筋」が見えると、不安が減り、自然とやる気が湧いてきます。
たとえば、職場で「なんとなく頑張ろう」ではなく、「3ヶ月で○○を達成する」という具体的な目標を共有するだけでも、モチベーションに差が出ます。
アドラー心理学では、**「目的論」**という考え方が重視されており、「人は過去ではなく、未来に向かって動く」と捉えます。
やる気が出ないときは、「目的がぼやけていないか?」を見直してみることが有効です。
📏 目標の高さとやる気のバランス
目標の設定にはもうひとつ大切な視点があります。それは、「高すぎず、低すぎないこと」。これは心理学でいうチャレンジ可能性と関連しています。
- 目標が高すぎると…「どうせ無理」と感じて最初から諦めてしまう
- 目標が低すぎると…「やっても意味がない」と感じて熱意が湧かない
理想は「少し頑張れば届きそうなライン」に設定すること。アドラーも、完璧を求めず、“勇気づけながら成長していく過程”を大切にする姿勢を強調しています。
僕自身、コーチングの現場では「まず1週間、毎日5分だけでいいから始めてみよう」という小さな目標を提案することがよくあります。
それが習慣になってくると、「次は10分やってみようかな」と自然にやる気が湧いてくるんです。
勇気づけとは、「やる気を押しつける」のではなく、「やってみたいと思える状態を一緒に作る」こと。小さな目標設定と、その達成への共感が、モチベーションの土台になります。
2-2. 内発的⇄外発的動機付けの違い
やる気には大きく分けて2種類の動機があります。
それが、内発的動機付けと外発的動機付けです。
この違いを理解することで、「なぜ人がやる気になるのか」「どんな関わりが効果的なのか」がより明確になります。
🔥 内発的動機付けとは
内発的動機とは、「自分の内側から湧いてくるやる気」のこと。
たとえば、以下のような感情が当てはまります。
- 純粋に楽しいからやる
- 自分の成長を感じられるから続けたくなる
- 好奇心や探求心が満たされるから頑張れる
心理学者デシとライアンの「自己決定理論」では、内発的動機は以下の3つの欲求が満たされると強化されるとされます。
- 自律性:自分で選んでいるという感覚
- 有能感:自分にはできるという実感
- 関係性:誰かとのつながりや信頼
つまり、内発的動機は“自分の意思”がベースになっているため、継続性が高く、持続的なやる気につながるのです。
🎁 外発的動機付けとは
一方、外発的動機とは「外から与えられた報酬や評価によって生まれるやる気」です。
- ご褒美があるからやる(お金・評価・賞与など)
- 叱られたくないから頑張る
- 周りの目が気になるから手を抜けない
こうした動機は、短期的な行動には効果的ですが、報酬がなくなったり、圧力が下がると行動も止まりやすいという性質があります。
🧠 どちらも活かし方が大事
「外発は悪、内発が正義」と考えがちですが、実際はどちらも状況によって活かすことが大切です。
たとえば…
- 子どもが勉強を始めるきっかけとして「終わったらシールあげるね」は有効(外発的)
- 勉強の中で「できた!」「分かってきた!」という感覚が芽生えれば、内発的動機に移行
僕自身、記事制作の仕事では「納期」や「報酬」という外的要因も原動力になっていますが、最終的には「誰かの役に立てる」という内発的な思いが、継続の力になっています。
やる気を引き出すには、「相手が何に価値を感じているか」を丁寧に見極めながら、外からのきっかけを内側の意欲へと橋渡ししていくことが大切です。
2-3. フロー理論 × 目標挑戦バランス
「気づいたら、時間を忘れて没頭していた」
そんな経験はありませんか?
それこそが、心理学者チクセントミハイが提唱した**「フロー(Flow)」**の状態です。
フローとは、集中と充実が高まった“究極のやる気状態”のこと。
この状態を生み出すには、「今の自分の能力」と「目標の難易度」のバランスが鍵を握ります。
🧩 フロー状態が生まれる条件
チクセントミハイによれば、フローに入るためには以下の3つの条件が必要とされます。
- 明確な目標があること
- 課題の難易度と能力が釣り合っていること
- 即時のフィードバックがあること
これを図で表すと以下のようになります。
| 状況 | 感情 |
|---|---|
| 難易度が高すぎる × 実力が低い | 不安・挫折感 |
| 難易度が低すぎる × 実力が高い | 退屈・無気力 |
| 難易度と実力が釣り合っている | フロー(集中・没頭) |
つまり、やる気を引き出すには、「ちょっとだけ背伸びが必要な課題」が最も効果的なのです。
🧠 フローの実例:卓球の試合から学んだこと
僕自身、全国大会に出場したとき、試合中に「相手の動きに無意識で反応していた」瞬間がありました。後で振り返ると、それがまさにフロー状態でした。
- 試合という明確な目的があり(目標)
- 相手の実力と拮抗していて緊張感があり(バランス)
- 得点やラリーごとに結果がわかる(フィードバック)
この3つが揃うと、「考えなくても動ける」ほどの集中状態になり、やる気は最高潮に達します。
💡 日常でもフローは作れる
特別な環境でなくても、以下の工夫でフロー状態はつくれます。
- 作業を細分化し、1つの明確なゴールを設定する
(例:「30分で構成だけ書く」など) - 時間を区切ることで集中しやすくする
(例:「25分集中+5分休憩」のポモドーロ・テクニック) - 進捗を“見える化”して即時フィードバックを得る
(例:タスク完了をチェックリストで可視化)
やる気を高めたいときは、「目標の高さ」と「自分の状態」が釣り合っているかを確認すること。
フロー状態は、努力や根性ではなく環境と設計でつくるものなんです。
次章では、人のやる気を形づくる「欲求理論(マクレランド)」について解説します。ご希望あれば、すぐにご提案いたします!
2-4. 欲求理論(マクレランド)と動機づけ
人が何かにやる気を出すとき、その原動力は人それぞれ異なります。
その「やる気の源」を3つに分類して説明したのが、心理学者デイビッド・マクレランドの欲求理論です。
彼は、人間には次の3つの基本的な欲求があり、どれが強いかによって行動の動機が変わると提唱しました。
1️⃣ 達成欲求(Achievement)
「目標を達成したい」「成果を上げたい」という欲求です。
- 成果を数字で見える形で得たい
- 改善や挑戦にやりがいを感じる
- 成長や上達に価値を見出す
こんな人には…
→ ゴールを数値化したり、「ここまでできるようになったね」と成長を可視化する声かけが効果的。
2️⃣ 権力欲求(Power)
「人や状況に影響を与えたい」「主導権を握りたい」という欲求です。
- 意見が通るとやる気が出る
- 責任のある役割に意欲を持つ
- 他者への影響力に喜びを感じる
こんな人には…
→ 意見を求めたり、リーダー的なポジションを任せるとモチベーションが高まりやすいです。
3️⃣ 親和欲求(Affiliation)
「人とつながっていたい」「仲間と協力したい」という欲求です。
- チームで動くことに安心感を感じる
- 共感やねぎらいにモチベーションが湧く
- 孤立や対立を避けたい
こんな人には…
→ 「一緒に頑張ろう」「助かってるよ」など、共感や感謝の言葉がやる気を引き出します。
🧭 欲求に応じた声かけが、やる気を生む
マクレランドの理論から学べるのは、**「人のやる気を引き出すには、その人がどの欲求を重視しているかを見極める」**ことの大切さです。
たとえば、達成欲求が強い人に「みんな仲良くやろうね」と言っても響きませんし、親和欲求が強い人に「もっと成果を出してよ」と言えばプレッシャーに感じてしまいます。
僕のコーチングでも、相手がどのタイプかを会話から読み取り、それに合わせた関わり方を意識しています。
「人によってやる気のツボは違う」。
この視点を持つだけで、日々の声かけや関わり方がグッと変わります。
次の章では、そうした多様な動機を活かすために重要な「共感コミュニケーション」について解説していきます。
2-5. 人を動かす「共感コミュニケーション」
どれだけ心理学的に理にかなった方法でも、「共感」がなければ、人の心は動きません。
やる気を引き出す本質は、相手の気持ちや背景に寄り添った“共感ベースのコミュニケーション”にあります。
🤝 共感とは「理解しているよ」という姿勢
共感とは、相手の気持ちを“代弁”することではなく、「あなたの感じていることに関心を持っている」という姿勢を示すことです。
- 「そう感じたんだね」
- 「それって悔しかったよね」
- 「その頑張り、ちゃんと伝わってるよ」
こうした言葉は、たとえ問題が解決していなくても、相手に“受け入れられている”という安心感を与えます。
この安心感が、やる気を回復させる第一歩になります。
🌱 具体的な褒め言葉の入れ方
褒めることも、ただ「すごいね!」と言うだけでは共感にはなりません。
相手が「わかってくれてる」と感じるには、“行動+背景”に目を向けた言葉選びが効果的です。
🎯 効果的な褒め方の例:
| シーン | 一般的な褒め方 | 共感ベースの褒め方 |
|---|---|---|
| 資料を早く提出してくれた | 早くて助かったよ | 「忙しい中、時間をやりくりしてくれたんだね。ほんとに助かった」 |
| チームでフォローしてくれた | 優しいね | 「相手が困ってるのに気づいて、すぐ行動できるのってすごいね」 |
| 提案が通ったとき | さすが! | 「あの提案、しっかり準備してたの伝わってきたよ」 |
💡 コツは、「その人らしさ」への気づきを言葉にすること
褒め言葉にその人らしい視点や行動が含まれていると、「ちゃんと見てもらえてる」と実感でき、モチベーションは自然と上がります。
💬 「共感→承認→勇気づけ」の順番がカギ
僕がペアコーチングを行う際も、
- 共感:「大変だったね。そう感じるの、すごくわかるよ」
- 承認:「それでもここまでやってきたのは、本当にすごいこと」
- 勇気づけ:「次の一歩、一緒に考えてみようか」
という順で関わるようにしています。
共感を起点にすることで、やる気の火種は無理なく自然に広がっていくのです。
3. 実践パート:日常で使えるテクニック
ここまで、やる気にさせる人の特徴や心理学的な仕組みを見てきました。
最後に、日常の中で使える具体的なテクニックを5つに整理してご紹介します。
どれも今日から試せる内容ばかりです。無理に変えようとするのではなく、「ちょっと意識を変えてみる」くらいの気軽さで取り入れてみてください。
✅ 1. ナッジ:小さな選択の誘導
ナッジとは、行動経済学で使われる「そっと後押しする仕組み」のこと。
たとえば、「朝、机にメモを置いておく」「やる気が出る言葉を目につくところに貼っておく」といった環境の工夫が、自然な行動変容につながります。
📝 実例:ペアコーチングの相手が「運動が続かない」と悩んでいたとき、朝の靴下の上に運動着を置いておくよう勧めたところ、習慣化に成功。
✅ 2. 内発的動機の醸成:選ばせる工夫
やるべきことでも「自分で決めた感覚」があると、やる気が湧きます。
- 「AとB、どっちから取り組む?」
- 「どうしたらうまくいきそう?」と問いかける
選択肢を与えることで、行動への納得感と継続性が高まります。
✅ 3. エンパシー表現:共感+具体的な言葉
相手の気持ちに寄り添うときは、「わかるよ」だけではなく、その背景まで具体的に言葉にすることが大切です。
- 「そう思ったのは、責任感があるからだよね」
- 「悔しいのは、それだけ頑張ったからだよね」
これだけで、相手の気持ちは大きく軽くなり、「もう一度やってみようかな」という前向きな気持ちが生まれます。
✅ 4. リフレーミング:視点を変える声かけ
マイナスに見える出来事でも、言い換えることで前向きな意味づけができます。
- 「ミスが多かった」→「それだけたくさん挑戦したんだね」
- 「目標に届かなかった」→「どこまで来たかが見えたね」
リフレーミングは、やる気を下げる出来事に「成長の視点」を与える力があります。
✅ 5. 一緒に取り組む姿勢:伴走型の関わり
「応援してるよ」だけでなく、「一緒に頑張ろう」と並走する姿勢は、とても大きなやる気の源になります。
僕自身、あるコーチング相手から「あなたが一緒に考えてくれるから続けられた」と言われたことがあります。
アドバイスや指示ではなく、“並んで歩く感覚”が、勇気と安心を与えるのです。
これらのテクニックは、特別なスキルではなく、日々の関わり方に少しの意識を加えるだけで誰でも実践できます。
4. よくある疑問Q&A
❓Q1:「外発的報酬だけでやる気は続くの?」
A:短期的には効果的ですが、長期的には限界があります。
お金・ご褒美・評価といった“外発的な報酬”は、行動のきっかけづくりにはとても有効です。
たとえば、「達成したらポイントがもらえる」といった仕組みは、特に最初の一歩を踏み出す助けになります。
しかし、それだけに頼ると、報酬がなくなった瞬間に行動も止まってしまうという問題が起こりやすくなります。
🔄 解決のヒント:「外から内へ」橋渡す工夫
- 「やってみたら意外と面白かった!」
- 「成果が見えると、自分でも成長を感じられる」
- 「誰かに喜ばれて嬉しかった」
このような経験を通じて、外発的動機が内発的動機に切り替わることがあります。
僕自身も、最初は「依頼されたから」書いていた記事が、「読者の反応が嬉しくて書きたい」に変わった瞬間を何度も経験しています。
❓Q2:「一瞬のやる気と継続のやる気はどう違うの?」
A:一瞬のやる気は“感情”による刺激、継続のやる気は“環境”と“構造”の設計によるものです。
一瞬のやる気は、音楽や動画、誰かの言葉でグッと高まることがあります。
でも、それは長くは続きません。
ここで活用したいのが、フロー理論です(2-3で解説)。
🧠 フローで継続力を生む3つの工夫
- 明確な目標を小さく設定する
→「1日5分だけ」といったミニゴールをつくる - 難易度を少しずつ上げる
→「ちょっと頑張れば届くライン」が最適 - 即時フィードバックを得る仕組み
→ チェックリストや記録アプリなどで達成を“見える化”
このように、「やる気が出たときに始める」のではなく、「やる気が出なくても自然と始まる設計」にすることが、継続の鍵になります。
5. まとめ&行動喚起
やる気を引き出す人には、特別なカリスマ性があるわけではありません。
共通しているのは、「相手をよく見て、信じて、そっと背中を押せる」関わり方でした。
📝 各章の要点まとめ
Chapter 1:やる気にさせる人の特徴
- 心理的安全性や即時フィードバックが、土台として機能する
- 言葉の力でやる気を引き出す「魔法の言葉」がある
- 感覚刺激(音楽・映像・運動)で一瞬のやる気を生む
- 褒め方・叱り方ひとつで、相手の行動は大きく変わる
- 実体験を通じて、関わり方の違いが結果に表れる
Chapter 2:心理学から見るやる気の仕組み
- アドラーの「勇気づけ」が内発的な行動を支える
- 外発的と内発的動機、それぞれの特性を理解する
- フロー理論で「ちょっと難しい目標」に没頭する状態をつくる
- 欲求理論で人それぞれの“やる気のスイッチ”を見極める
- 共感ベースの褒め方・伝え方が人の心を動かす
実践TipsとQ&Aで得たこと
- 環境と習慣がやる気を設計する
- 「外→内」への動機の橋渡しがポイント
- 一瞬のやる気と継続のやる気は、性質も仕組みも異なる
🚀 小さな一歩を踏み出すあなたへ
すべてを完璧にやる必要はありません。
まずは今日、身近な誰かに「助かったよ」「ありがとう」と声をかけてみてください。
それだけで、あなたも“やる気を引き出せる人”の一歩を踏み出せます。
📣 ご案内:大戸勇輝のX(旧Twitter)で日々発信中!
やる気・習慣・コーチングに関する気づきや、日常のちょっとした学びを、僕のXアカウントでも発信しています。
記事の感想や、実践してみたことも気軽にリプライくださいね!
【僕がXで「発信」をする理由】
— 大戸勇輝|元卓球全国出場のコーチング🏓 (@yuki0629_mv) June 25, 2025
大学3年の冬、コロナで部活が止まった。
大会も練習もなくなって、気づけば同級生は次々と引退。
それでも、僕は卓球を続けることを選んだ。
ただその時、正直すごく悩んだ。
「1人だけ残って浮かないかな」
「後輩たちに気を遣わせないかな」… pic.twitter.com/D6VEHeZSNb